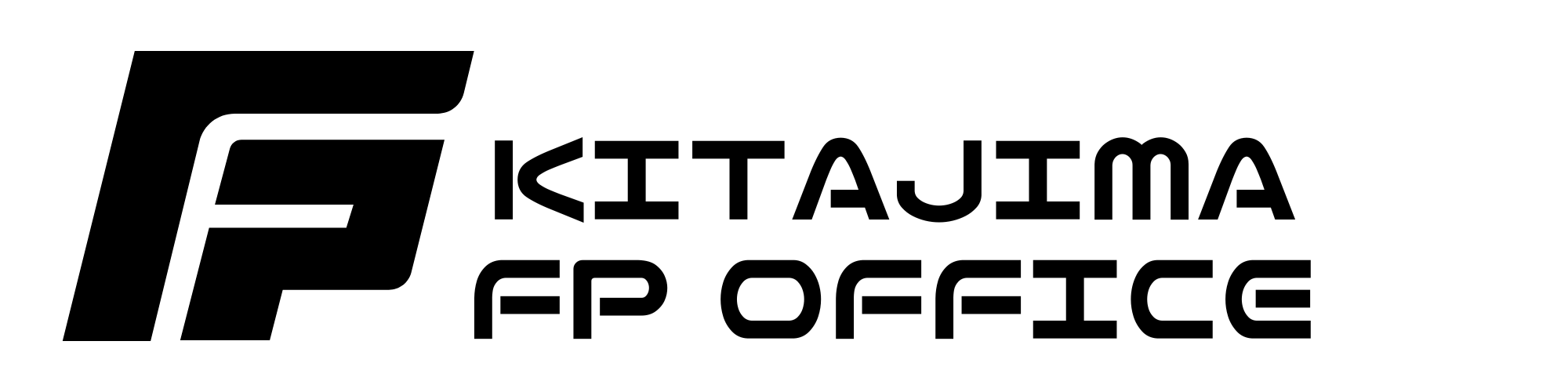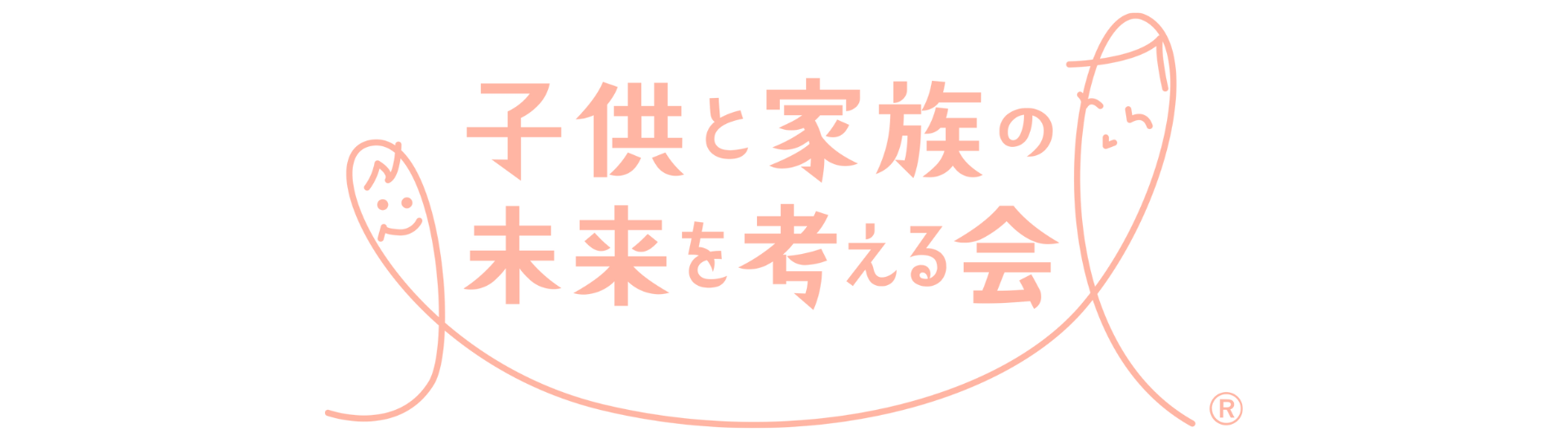国会での金融教育ワークショップ

「金融教育の拡大」へのワークショップを国会にて開催してきました。
狙いは「若者世代への金融教育の場の提供」と「国会議員への課題提起」です。
日本経済や社会の変化に伴い、金融教育の重要性がますます高まっており、金融詐欺や投資詐欺なども社会問題化している中、学生など若い世代が金融リテラシーを学ぶきっかけの場を作りました。
通常の学ぶ場だけでなく、参加者も考えて「国会議員」など様々な立場の方を巻き込んで課題解決に繋げていくワークショップです。
■日程:2024年12月17日(火)
■場所:国会議事堂、ならびに衆議院第一議員会館 会議室
■参加対象:一般(中高大学生、保護者)、教育関係者
■登壇者:国会議員、弁護士、高校教師、金銭被害の経験者、FP(ファイナンシャルプランナー)
学校における「お金の教育」の導入とその課題
講師:現役の高等学校の教師


学校でのお金の教育の現状
■各学校での状況
・小学校
社会・生活・家庭科・道徳・特別活動を中心に全教育活動を通じて推進
・中学校
ライフプランニングの理解、金融機関の機能について社会科の公民分野で学ぶ
・高等学校
ライフプランニングの方法、電子マネーや決済機能など実践的な知識を学ぶ。主に公民・家庭科・商業の授業を通じて学ぶ
■高等学校での実態
・生徒
公民や家庭科は、他のメイン教科(英、数、国、物理、化学、地理、世界史、等)と比べると大学受験と直接関係ないため、優先度が下がる。
・先生
公民専門の教師も家庭科専門の先生も、「金融」分野に詳しいとは言えない。(むしろ専門外)
そのため、教える側の底上げも必要。
教育現場の先生の困惑
- 金融教育の一つの大きなテーマである「資産運用」の話を一生懸命話すほど、金融商品を推薦している様にも聞こえてしまう。
- 学校の先生は「資産運用」をやったことない人がたくさんいる
→あまりお金に困っていない。社会的責任で仕事をしており、あまり自分の家計に、そんなに執着しない人が多い。
- 学問なのか?という疑問
専門家に任せるという考え方
- 証券会社や銀行の講演で代替するという学校も結構多い
→特定の利害関係があるため、本当に良いかどうか分からないが、やっぱり専門家に任せるべきという考え方
- 学校によってもばらつきがあるし、先生によってもこれ扱い方にばらつきがある
- 教える期間に必要なこと
判断に必要十分な説明をすること
わかりやすさ、公平性、リスクと可能性
- 学校/家庭でも「判断ができる思考力や判断力を育てる」ことが必要。
また、欲望と倫理観が対立することもあり、難しいのも事実。
お金をどう使うのかをきっちりと考えさせる
①まずは自分のため
老後、就労、災害、病気、物価高などのリスク
②夢を実現するため
自分が何をしたいのか?目標、夢、志
③社会貢献
自分に何が出来るのか、社会にどう役立つのか、どんなインパクトを社会に与えられるのか?
金融詐欺の手口と防止策
講師:弁護士


金融トラブルとは?!
例えば、
- 投資や暗号資産などの儲け話に誘われる
- 儲からない情報商材を購入してしまった
- SNSでモニターに参加し不本意な契約をしてしまった
- フリマアプリで偽物を購入してしまった
- 推し活に熱中して高額な転売チケットを購入してしまった
結果、
- お金が返ってこない
- 大損をした
- 話が違う
- 裏切られた
- 連絡がつかない
今回は「詐欺」をピックアップ
詐欺とは
「人を騙して、お金や利益を騙し取る」
ダメージが大きい!
- せっかく守ってきたお金が…
- 金銭的ダメージ、精神的ダメージ
過去の詐欺事例
- モンゴルの金鉱山投資に1億円以上
- 不動産短期売買事業への出資に2500万円
- ベンチャー企業への出資に9000万円
- ホストへの貸金で800万円
- 高級腕時計投資話への出資で900万円
- 運送事業への出資で4000万円
など
自分は引っかからない?!
- 自分は注意深い?
- ニュースや噂で手口を知っている
ほぼ全ての人が引っかかる
- 老若男女問わない
- どんな職業、どんな年代の人も騙されてしまう(例えば、医師、弁護士、警察官)
なぜ?!
人の心理、欲につけ込んでくる
- 「(楽に)お金を増やしたい」
- 「不安を取り除きたい」
重要ワード(要注意ワード)
- 「確実に儲かる」
- 「絶対に返す」
- 「みんなやっている」
- 「ここだけの情報」
- 「間違いない」
詐欺界隈のプロの仕事内容
- それっぽい資料や契約書を出してくる「利回り30%」「金を発掘中」
- 著名人の名前を出してくる「〇〇ファンド」「〇〇選手」「〇〇の子孫」
- 大きな名前を出す「財務省が」「〇〇銀行が」
- 良い立地にオフィスがある
- 六本木や新宿など良い場所へ大きな看板広告
- 山手線の車内広告
- 実際に途中まで、配当金・出金がある
事例 エクシア合同会社
- 9000名以上からの出資
- 総額850億円以上
- 数百万円、数千万円の出資をした人も
- 途中まで配当があり、出金できていた
- しかし、2021年秋頃から出金できず
- ポンジスキームの噂は以前よりあった
- 多くのトラブル、訴訟に発展
→結果、破産
相手はプロ
①人間の欲は怖い
(周りが見えなくなる、冷静な判断が出来なくなる)
②相手は、緻密かつ用意周到な手口で詐欺を仕掛けてくる
疑っても、それを上回るプロ
「あれ見せてください」→「はい、どうぞ」
こちらの疑問をクリアしてくる。
「Netflixドラマ 地面師たち」
・リーダー・・・計画
・情報屋・・・土地、所有者の調査
・法律屋・・・段取り、交渉
・ニンベン師・・・文書偽造
・なりすまし役・・・地主へのなりすまし
親しい人、身近な人、いい人だと思っていても
あなたのお金を狙っている!
お金が返ってくることは無い?!
基本的にはお金は返ってこない
投資も貸金も。
裁判で勝っても返ってこない。
(理屈ではない)
「では、どうすれば??」
どんなことに気をつけるか?
- 相手は手強い
- 人は見たいものを見る、相手は自分が見たいものを見せてくる
- 自分で判断できるか
- 怪しいという直感を大事に
- 周りの複数人に相談する
- 「うまい話」な無いと知る
- 許容できるリスクか確認する
- 担保を取る
大事なお金を守りましょう!!
国会議員との意見交換
土田 慎 衆議院議員(自民)
宗野 創 衆議院議員(立憲民主)
一般参加者
ファシリテーター:FP (ファイナンシャルプランナー)






- 昨今物価上昇が激しいが、それに伴って賃金上昇は追いついてないよねというのがやはり誰もが思っている。そこに対して政治としてどうやっていくかとか、政治家としてどう取り組むべきか、いろいろ検証しながらバランスを取りなが考えている。
- いろんな立場の人が、こっち立てばあっち立たずみたいなことに起きてしまう。例えば、日本人よりも外国人が優遇されているという声もありました。それも意見としてはある。やっぱり日本という国を考える上で、バランスを取っていくことが大切。
- 失われた30年と言われているこの日本で、経済成長をこれからどうやって遂げていくか、また生活を豊かにしていくか、具体的にこうすれば改善するというのはなかなか難しいとは思うんですけれども、やっぱりもっと若い層がですね、政治に目を向けて、国に目を向けて、意見を出し合っていく。
- 今日のこの様な場は非常に貴重でもっと増やしていくべき。
まとめ
- 「社会で生きていくための必須知識、生きる力、人間力の習得」という目的に向かって「金融教育」をさまざまな世代で浸透させていく必要があると感じた。
※他の教科でも「受験のための」勉強になっていることが多々あり、社会でどの様に活かせるか、活かすか、までしっかりと考えられると良い。
- 様々な社会課題が山積している中、政治の世界ではバランスを考えることは必須。その中で、関係する方々に課題提起しつつ、「金融教育」の取組みを継続していきたい。